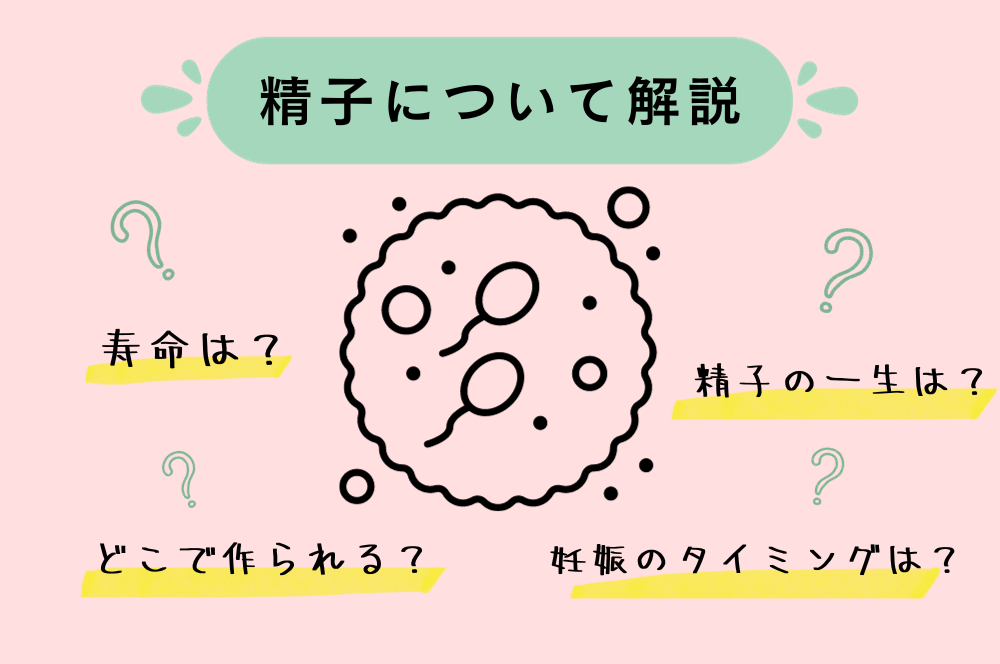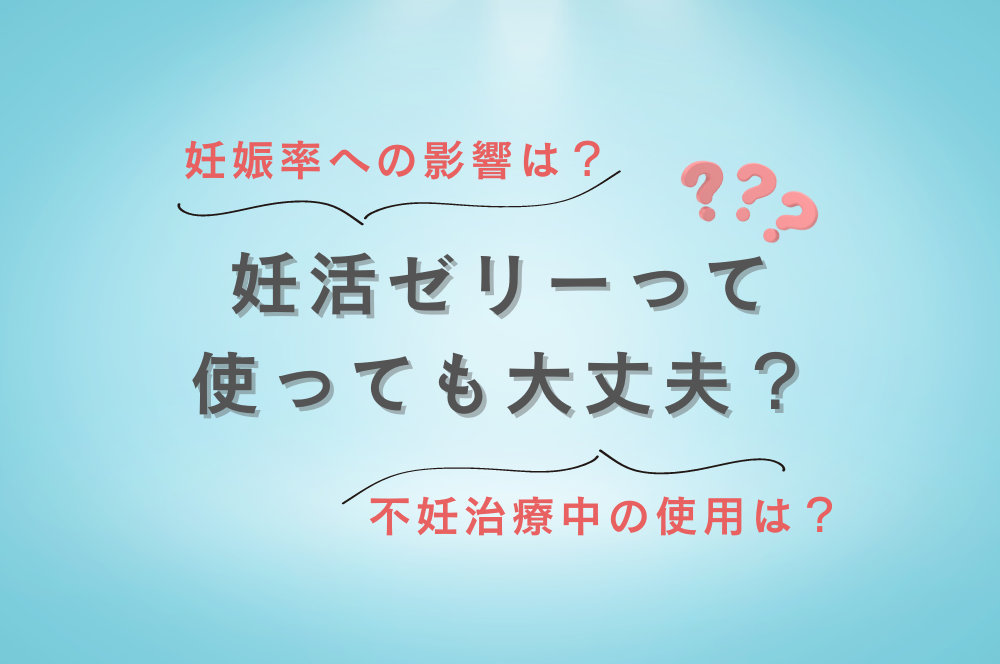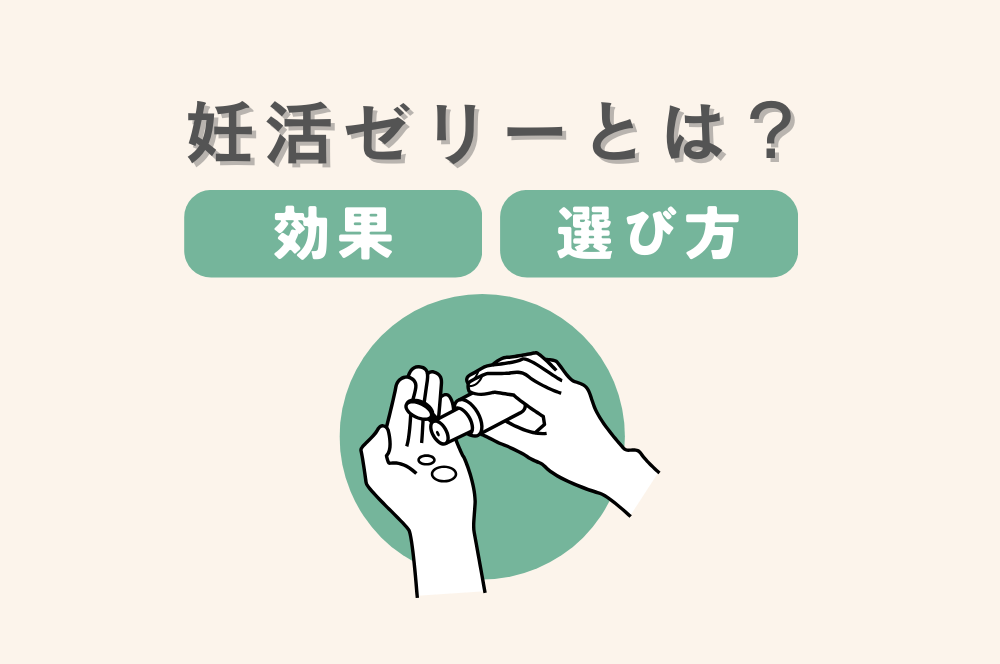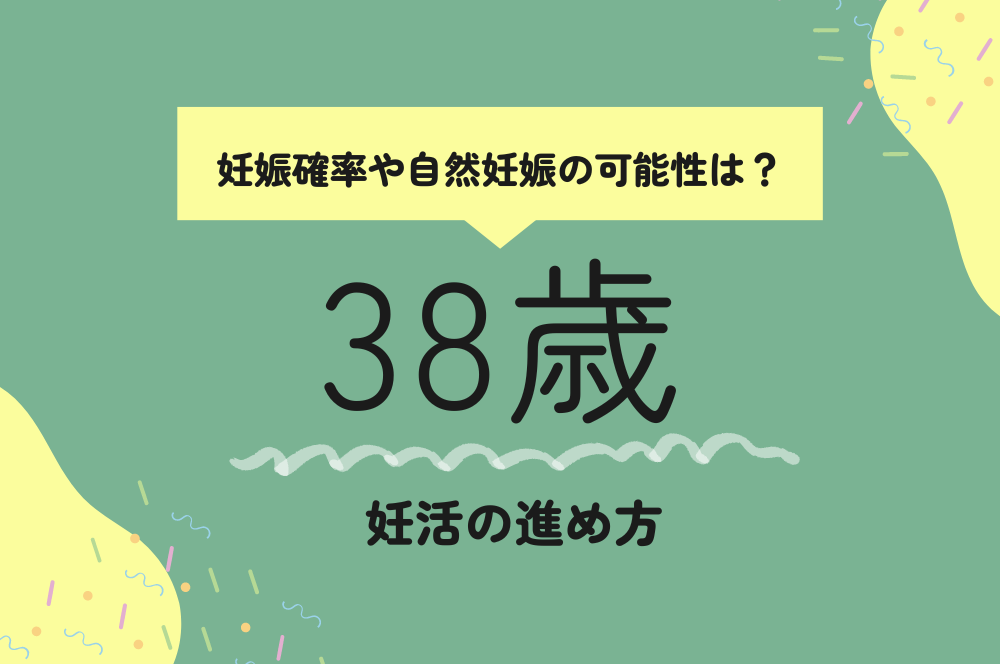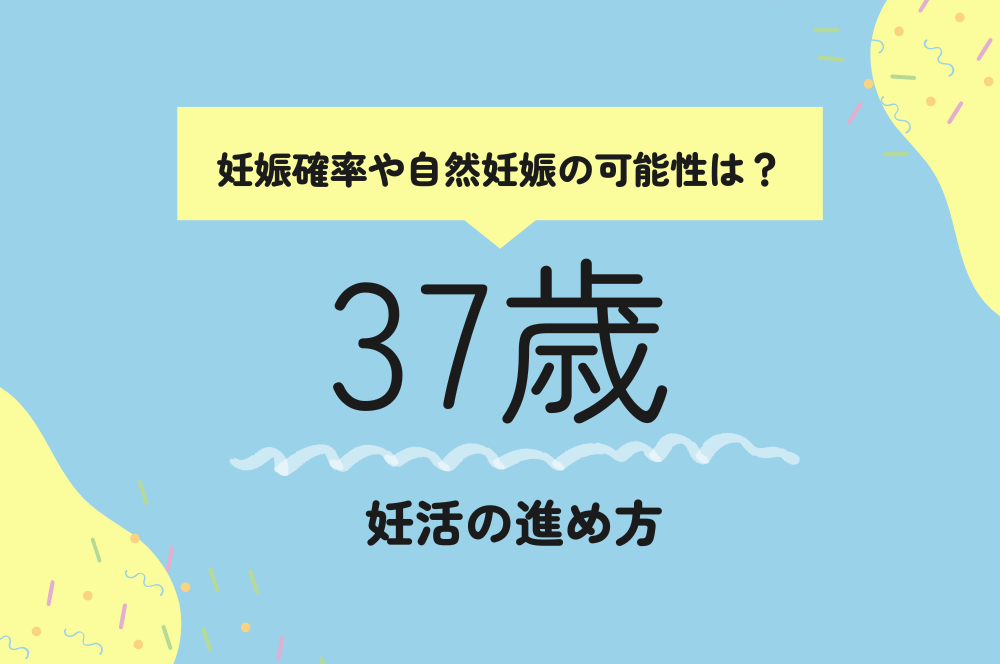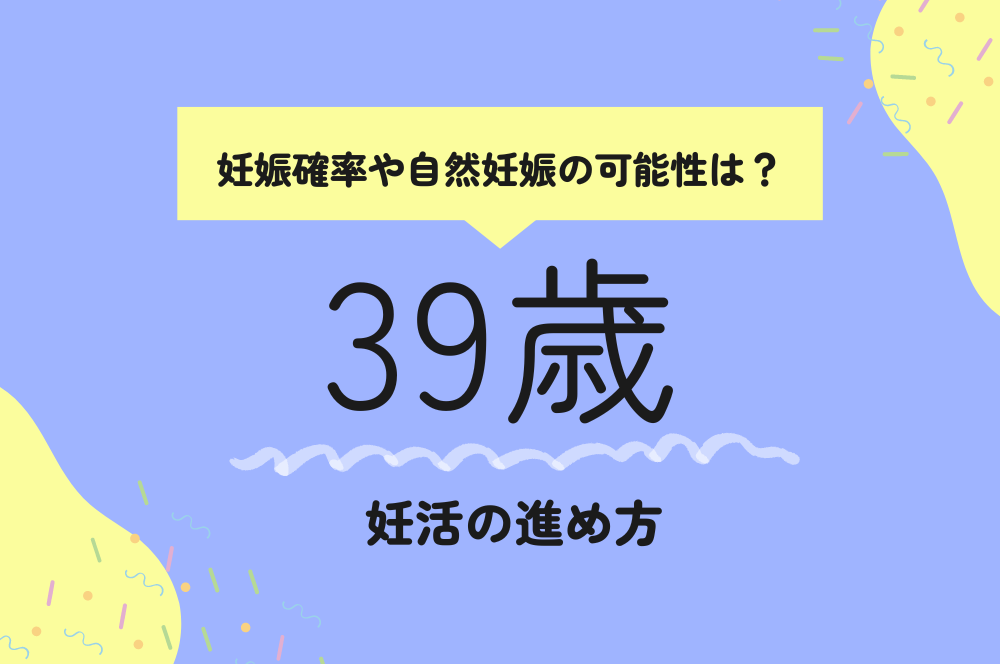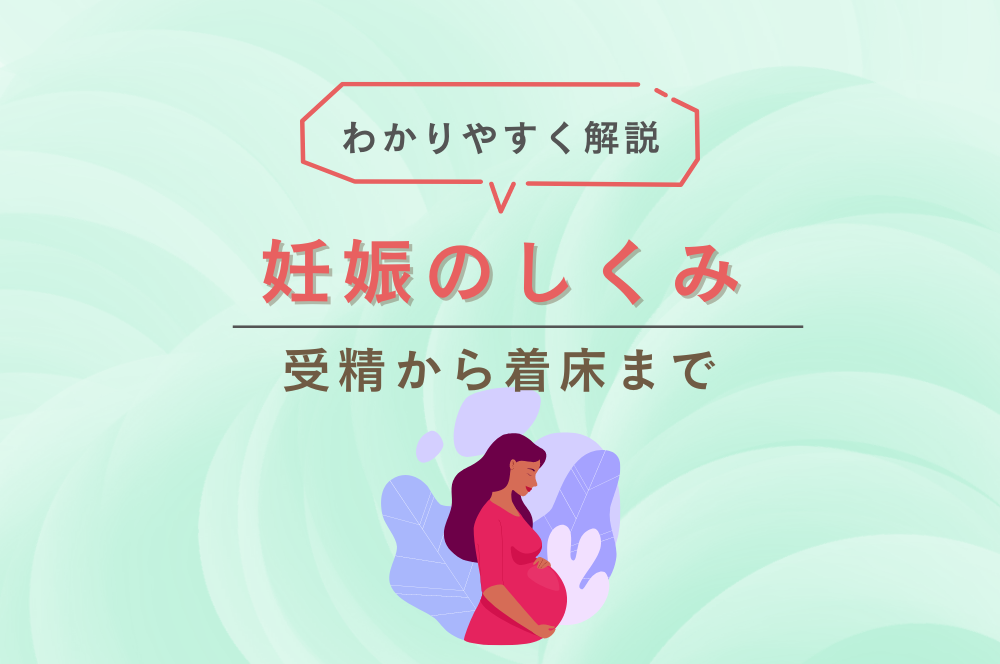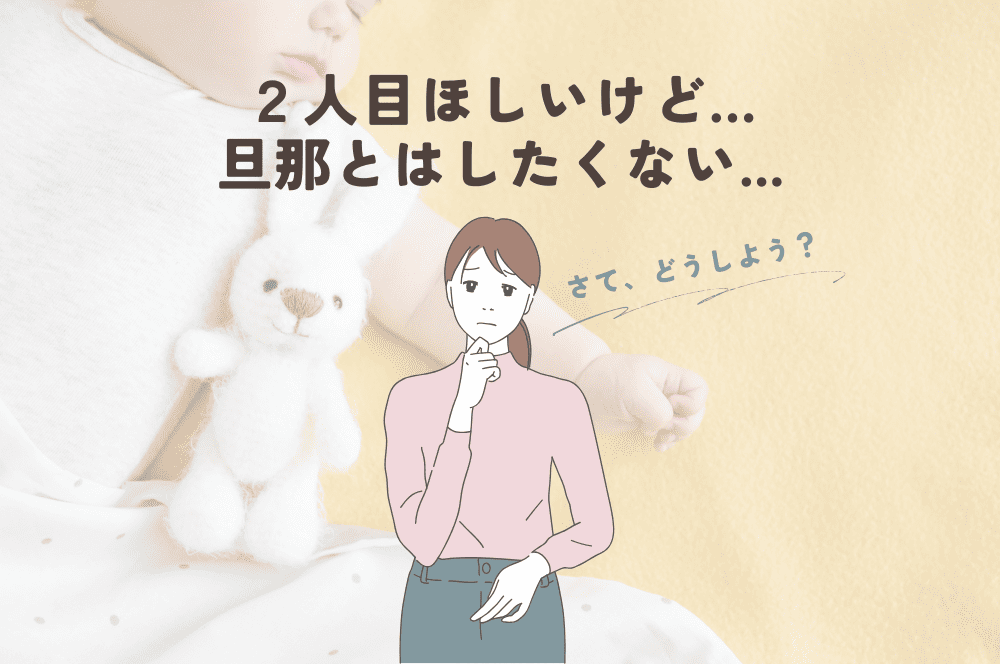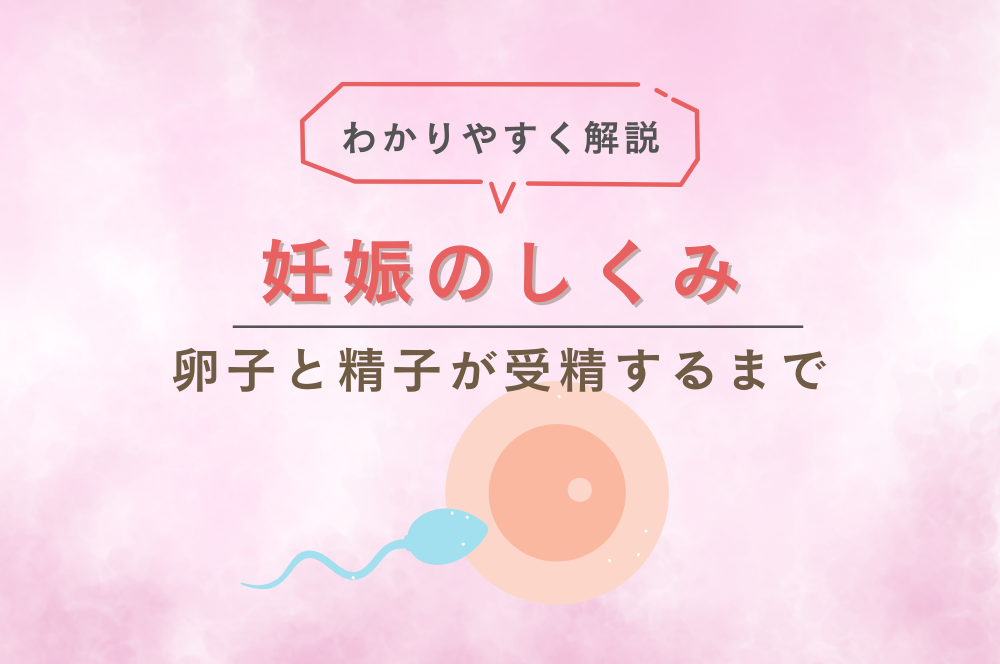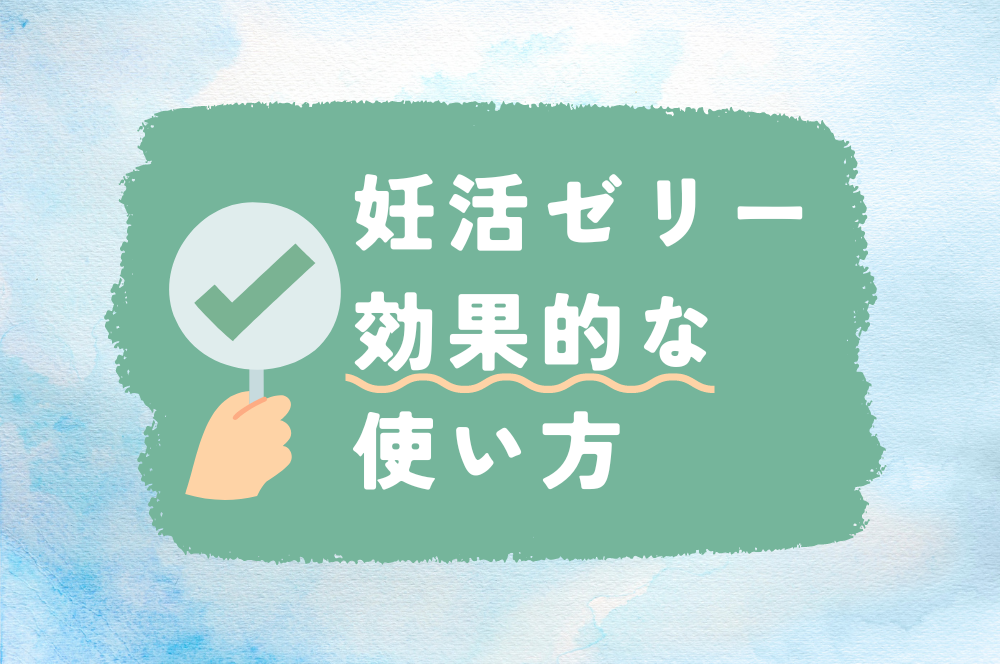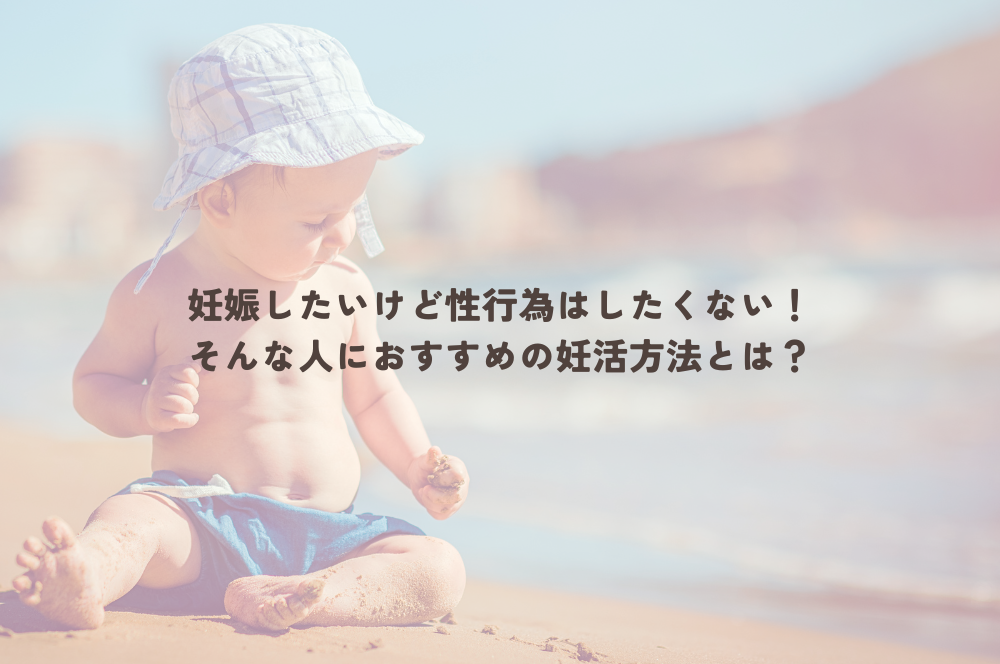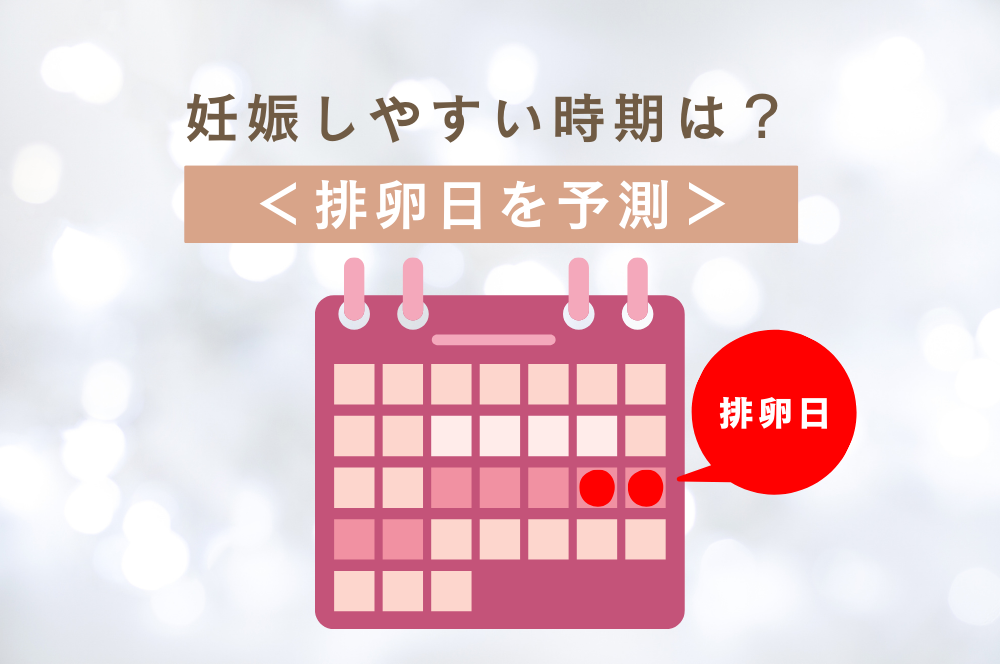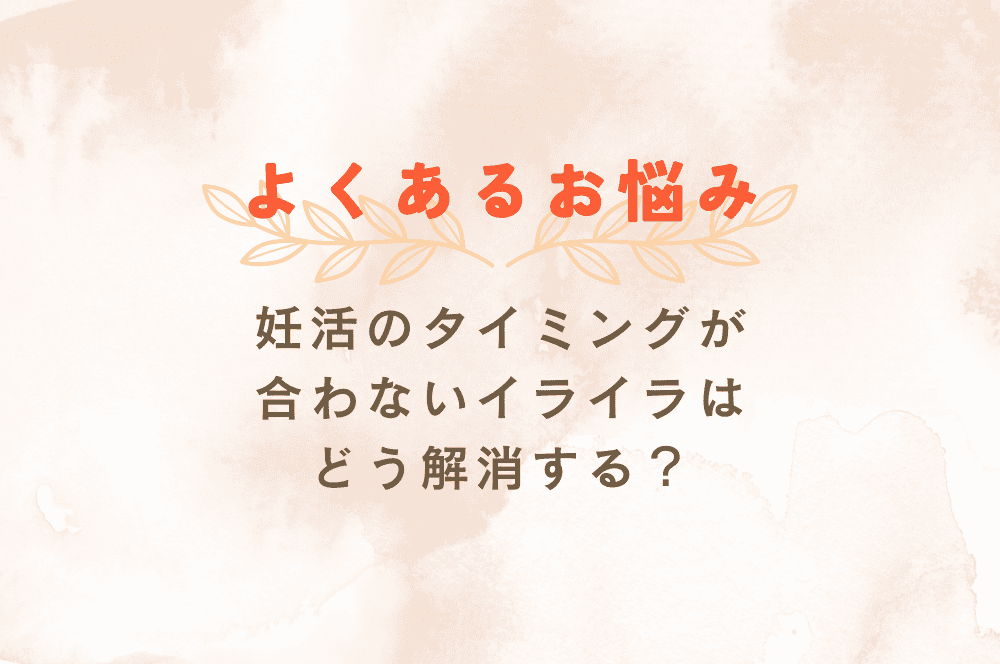【特別インタビュー】東尾理子さん~誰もが適切な時に適切な妊活や生殖の知識を得られる社会を目指して~
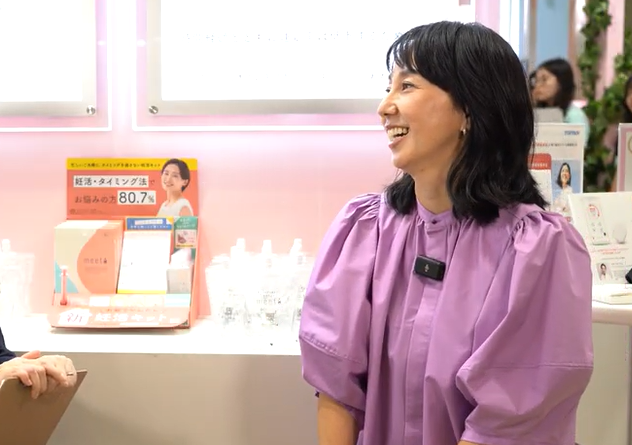
第3回Femtech Tokyoのブースにて、ベビーライフ研究所が主催する「妊活アワード2024」が開催されました。タレント部門「レジェンド賞」を受賞した、プロゴルファー・タレントの東尾理子さんにインタビューを行いました。
東尾さんが妊活に関わる活動を始めたきっかけやご自身の妊活体験、そして代表を務めるNPO法人TGPの活動内容と目指す未来について詳しく伺いました。
オンラインコミュニティ「妊活研究会」の立ち上げ
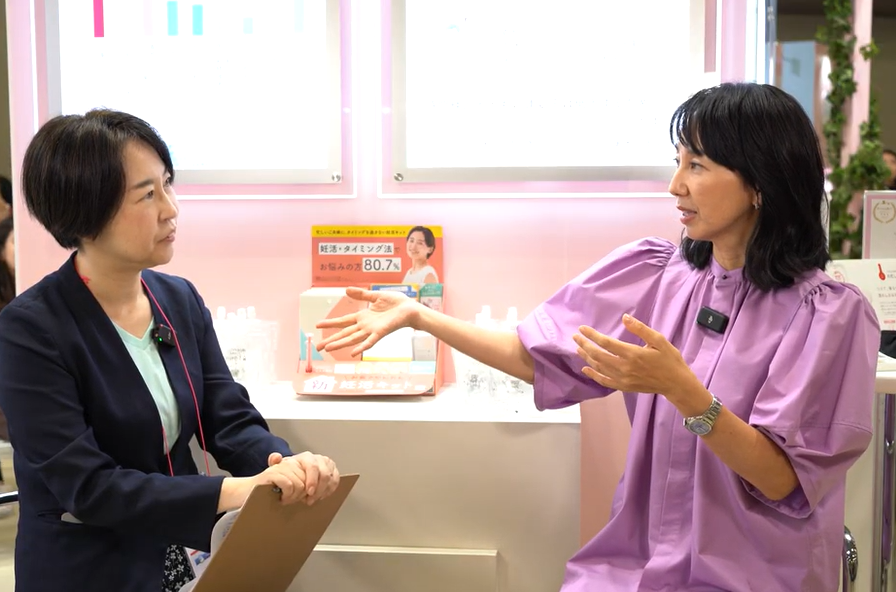
東尾さんは、第一子を授かろうとした時からボランティア活動を始めました。当初はそれこそボランティアのつもりではなく、その時本当に妊活に関する情報が全くないと感じて「何をどうやるのか」「妊活に関する実際の話を聞きたい」と思い、全国でお話会を開催したそうです。
コロナ禍で対面活動が難しくなった際には、オンラインで話し合いの場を設けることで、国内にとどまらず海外の人々ともおつながりができました。この経験から、妊活当事者の心のサポートや新しい情報の提供を中心に据えた「妊活研究会」というオンラインコミュニティが生まれました。
若者に向けての正しい性教育の普及
TGPでは妊活当事者の心のサポートや、最新の妊活情報をお伝えすると、東尾さん自身もそうだったように「妊娠に適齢期があるなんて思っていなかった」「もっと早く知りたかった」などの声が多かったのです。
そういう声をなくしていくためには、やはり若者・学生向けの早い段階での教育が重要だと感じました。
そこで、TGPでは【妊活されている方へのサポート】と【若者向け生殖教育】の二軸で活動しています。特に力を入れているのが、性教育を通じた正しい生殖知識の普及です。
性教育に対する抵抗感が根強い日本社会で、東尾さんは「命をつないでいくための知識」として、小中学生、高校生、大学生といった若い世代に向けた教育プログラムを計画しています。変な話、メダカの卵子と精子の受精は教わるのに、ヒトではしないですよね。
しっかり「女性の生理」や「男性の機能」を、ユネスコのセクシャル教育ガイダンスを基に、小学校高学年から命の授業を行い、生殖について正しく学ぶ場を作ることを目指しています。
家庭でのオープンな会話と日常からの学び
東尾さんは、家庭でも性教育について会話する機会はあると言います。例えばお風呂でフェムケアゾーンに使う石鹸について「なぜ違う石鹸を使うの?」と聞かれたら、「大切にするところだからだよ」と教えたり、妹たちとお風呂に入りながら話してみたりとか、日常的な会話を通じて自然と性について学べる環境を作っています。
また息子さんがクラスメイトといっしょに助産師に授業をやっていただいた時には、その瞬間は特に変化はないのですが、いきなり3ヶ月とか半年後にあの時の授業はこういうことだったみたいな感じで話すこともありました。知識として蓄積されているのだと思います。
生理ナプキン常備の推進
女性の性と切り離せないのが「生理」です。小学生や中学生は、生理の時にポーチとか持って歩くのは嫌ですよね。
少しでも快適に学校生活を送れるよう学校のトイレ個室に生理ナプキンを常備することを目指し、支援しています。
これまで多くの学校では、生理ナプキンを置いておくのが保健室であったそうです。それは、「男性がトイレットペーパーを保健室に取りに行くくらい不便なこと」と具体的なたとえ話をすると、なるほどと納得されやすいです。こうした活動も、TGPに寄せられる募金によって支えられています。
東尾さんの妊活に対する考え方

ここからは、東尾さんの妊活に対する考え方を伺いました。当時不妊治療について公に語ろうと思った理由は、「子供を作ろうと頑張っていることは、何も悪いことでも恥ずかしいことでもない」と考えていたからです。
「隠す必要はない、昨日何をしたのか話すように普通に話せばいい」と彼女は言います。公表してからは、「実は私もね」と言って、多くの方が声をかけてくれたそうです。本当はみんな不妊治療について話したいし、相談したいのだけれど、言いづらいし、言える場がなかったのだなと強く感じたそうです。
パートナーとの妊活への取り組み方
不妊治療中は、東尾さんは夫である石田純一さんと一緒に病院に行くことを大切にしていました。「自分だけが先生からの話を聞いて、それを夫に伝えると、どうしても伝わるインパクトが1/10ぐらいになってしまう」だから夫婦で同じ情報を共有することで、二人の問題として向き合うことができると考えていました。それが「パートナーがいっしょに病院に行ってくれるなんて協力的ですね」って言われてしまうのが、どうなんでしょうか。夫婦での協力が当たり前であって、普通のことと思われる世の中になるといいですね。
また、妊活の中でのタイミングには「無理なものは無理」と割り切って対応していました。「私たちのタイミングが合わなければ、その日はその日じゃない」と、無理をしないスタンスを大切にして過ごしていたそうです。
そこで思い切って「もし当時、meeta(ミータ) シリンジのような妊活タイミング法キットがあったなら使っていましたか?」と質問してみたところ、「使っていたと思います」とのこと。
シリンジも不妊治療も、将来自分に必要になるかは別として「妊活に関して自分が選択できるように、より多くの知識を持つことが大切」と考え、若い時から妊娠適齢期を意識し、正しい情報を手に入れることの重要性を伝えています。

不妊治療の中でぶつかった壁
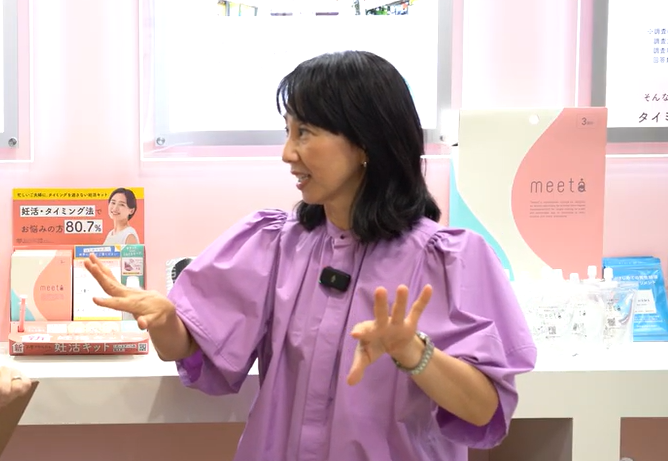
東尾さんが不妊治療の中でぶつかった壁として、「努力してもお金をかけても、何も結果がないものってなかなかないと思うから、その理不尽さを何で味あわなくてはならないのだろうっていうのをすごく思っていました。
たとえば修行じゃないけれど普通ダイエットとかなら、頑張れば結果として痩せるとか何かしらあるけれど、治療しても結果がでないことが悩みでしたね。」と振り返る東尾さん。
それこそ、これまで結婚した人に向かって『子供は?』って当たり前に聞いていたけれど、それって実はすごく繊細なトピックだったのかなと。知らずに傷つけていた人がいたかもしれないっていうのはすごく学びました。だからこそ、その経験を通して【治療はしないに越したことはない。若いうちに知識を持って、自分の選択を大切にしてほしい】と心から願って、現在も活動を続けていらっしゃいます。
最後に
東尾さんは、ご自身の経験を基に、多くの妊活中の方に情報を提供し、心の支えとなるコミュニティを提供しています。また、若者への生殖教育の普及や生理ナプキン常備の活動は、社会全体の意識改革を促すものです。
夫婦での協力は重視しつつも、無理をしないスタンスが共感を呼び、新しい選択肢を考えるきっかけになると思っています。もっと東尾さんの活動を詳しく知りたい方はNPO法人TGP「妊活の歩み方」サイトへ
▽タイミング法キット meeta シリンジをもっと知りたい方

本記事の執筆者
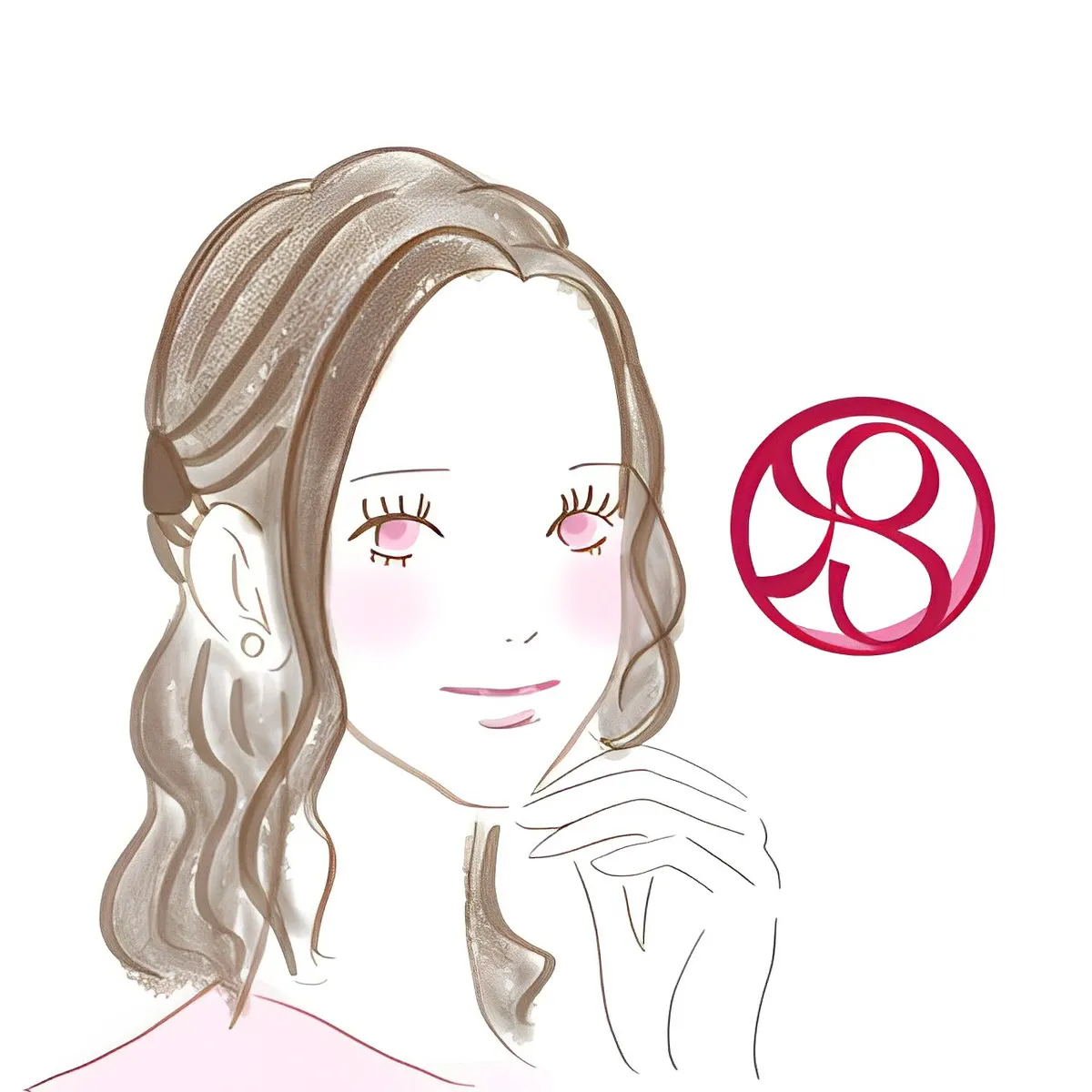
ベビーライフ研究所編集部
ベビーライフ研究所では、妊活に取り組む多くのご夫婦に向けたタイミング法キットや栄養補給サプリメント等の商品を取り扱っています。
私たちが長年培ってきた妊活の知識や経験を活かして、より多くの方に正しい情報を発信いたします。

お得なクーポンを随時配信!